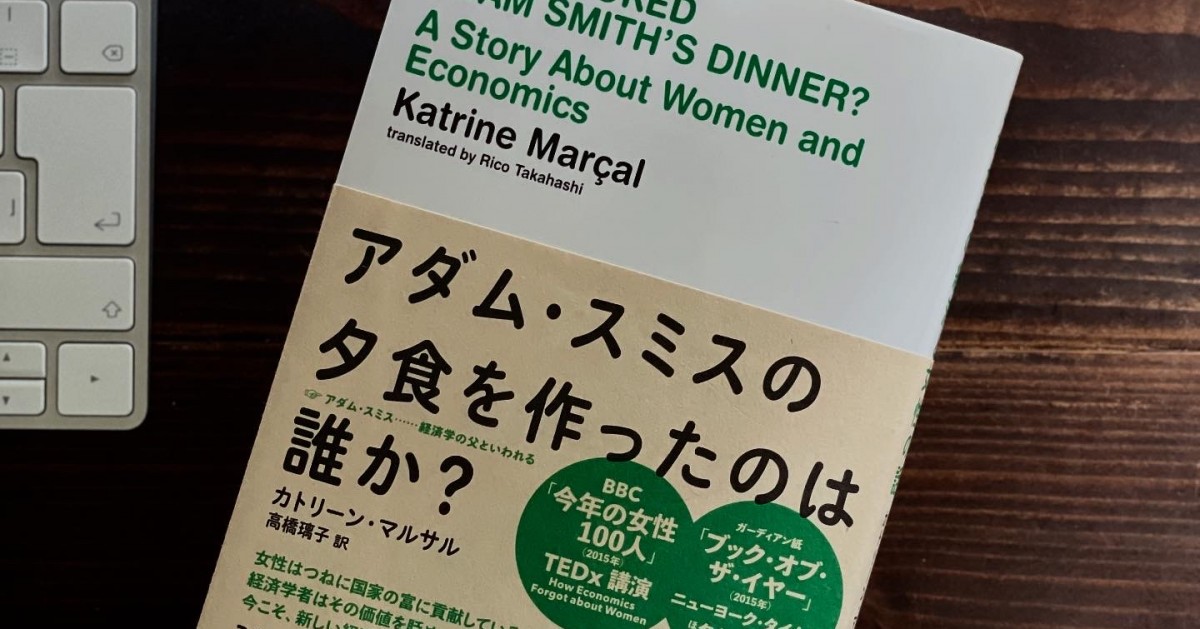【Wildflowers Letter vol.24】「彼女」はわたし
こんばんは。今日は労働と家事の一切を放棄しました、ミホ子です。
50年前の1975年10月24日、アイルランドの9割の女性たちが職場や家庭内における仕事を一斉に「休む」という、ほかに類を見ないムーブメントが起きました。もちろん国は機能不全となり、女性たちがいなければ社会をまわすことはできないという事実がはっきりと証明されたのでした。そんな最高にイケてる彼女たちを追ったドキュメンタリー映画『女性の休日』が明日25日から公開されますので、全員観にいきましょう。
こういうことにはきちんと便乗しなくては。ということで本日は自主休日。まぁ、これ書いてますけどね。でもこれは労働ではないので、ノーカウントで。なんか、これからも定期的に家族や友達、恋人たちと結託して、抵抗としての「休日」を敢行していきたいなと思いました。だって国がどんどん働かせようとしてくるんですもん、ストライキじゃストライキ。

最高な笑顔。
溜まっている台所の食器たちは日付が変わったら片付けます。本当です。
恐る恐る翻訳してみる
最近趣味で洋書の翻訳をしています。いや、翻訳といっては怒られるほどChatGPTとの二人三脚がすごいのですが。もはや二人二脚です。竹馬状態です。
翻訳しているのは、シャーロット・パーキンズ・ギルマンの代表作である『The Yellow Wallpaper』。19世紀の終わりに発表されたフェミニズム文学の金字塔とも言える自伝小説です。毎日ワンセンテンスずつ翻訳しているのですが、これが実になかなか楽しいのです。
今わたしの手元にあるのは2012年にヴィラゴ・プレスから出版されたペーパーバック版なのですが、春先のロンドン滞在時に偶然の出会いをはたし、開いてみれば乱丁本だったりと色々思い入れ深い子でして。英語が読めないくせに原書を買うなんてさぞお気に入りの小説なのかと思われるかもしれませんが、実はずっと翻訳された本が流通していないと思っていたのもあり、読んだことがありませんでした。最近、西崎憲さんによる日本語訳(『淑やかな悪夢 英米女流怪談集』収録)が存在することを知ったのですが、せっかくなので自分で訳してから読み比べたら面白いのでは?と思いついてしまい、いつかのお楽しみにとっておいているのです。つまり、ぼやぁっとしたあらすじしか分かっておりません。あとはフェミニズム文学の系譜上、重要な作品であるというイメージを持っていたくらいで。しかしこの小説、というかまだイントロダクションしか翻訳できていないのですが、すでにめちゃくちゃ身につまされています。え、どういうこと?
本書の前書きは作家Maggie O'Farrellさんによるもの。彼女は『The Yellow Wallpaper』が発表された当時、ボストン・トランスクリプト紙に掲載されたとある男性医師による抗議文を引用します。
"The story can hardly, it would seem, give pleasure to any reader such literature contains deadly peril. Should such stories be allowed to pass without severest censure?"
「その小説はどんな読者にも喜びを与えることはできないようだ。このような文学には致命的な危険がはらんでいる。そのような小説がもっとも厳しい非難を受けずに世に出ても良いのだろうか。」
匿名での根拠のない批判、今で言うクソリプをかましているわけですね。死に至る危険をはらんだ小説とは一体…。今でこそ笑えますが、約130年前には実際にこういった投書が公然と発表されていたのですから、人間も少しはマシになったといえるのかもしれません。
この物語の主人公はある名もなき女性。一時的な神経衰弱を患った彼女は、療養という名目で医師である夫に屋根裏部屋に閉じ込められてしまいます。
I am absolutely forbidden to "work" until I am well again. Personally, I believe that congenial work, with excitement and change, would do me good. But what is one to do?
「私は、また元気になるまで『働くこと』を固く禁じられている。私としては、刺激と変化のある自分に合った仕事こそが、わたしのためになると信じている。けれど、どうすればいいというのだろう。」
その答えは、彼女にできることは何もない、ということ。
Slowly suffocating under the wrong kind of case, she is forced to dwell on the only things in front of her: the room; the grim bars on the windows; the bed, screwed to the floor; and the peculiar repetitions of the patterned, yellow wallpaper.
「誤った治療のもとで次第に息苦しくなり、彼女は目の前にあるものにばかり意識を向けざるを得なくなる。部屋そのもの、窓を覆う陰鬱な鉄格子、床に打ち付けられたベッド、そして黄色い壁紙の模様に潜む奇怪な反復」
特に苦しい一節。わたしもこの景色に見覚えがある。
重度の産後うつを抱えていたギルマンが実際に受けた誤った治療により、精神崩壊寸前まで追い込まれたことに対する怒りのエネルギーで書かれた本作。その魅力を熱く書き連ねたいのですが、本編の翻訳はこれからなので詳しい内容についてはまだ今度…。はたしていつになるのやら…。こんな具合に定期的に進捗報告していこうと思いますので、気長にお待ちいただければ。一緒に『The Yellow Wallpaper』を読み解いていきましょう。
ちなみにわたしの英語力は中学生レベルなので、基礎的な単語や文法すら一々辞書で引いたりChatGPTに聞いたりしないと二進も三進もいかないわけですが、逆にそれが功を奏しているのか、今までこんなに一語一句のディティールや意図、時代背景をじっくり噛み締めながら本を読んだことがあったか?と自問せずにはいられないほど、新たな読書の境地を開いている気がしています。そしてそれのなんと豊かであることか。もしかしたらネイティブ言語である日本語では体験し得ない感覚かもしれません。あと、しばらく続けられそうだったので思いきって紙の辞書を買ってみました。わーい。しかも革装。最初はスマホで調べていたのですが、だめでしたね。集中力が切れるし、身になっている気がせず。コスパやタイパといった言葉の対極にあることをしている自覚はありますが、そういう不便さや手間って嫌いじゃないんですよね。よく言えばクラシック。
彼女たちの語り直す術として
翻訳に関する話をもうひとつ。
T.S.エリオットっているじゃないですか。ノーベル文学賞を受賞した作家の。代表作は『荒野』『四つの四重奏』あたりでしょうか。あとはミュージカル『キャッツ』の原作を書いた人でもありますね。さて、後半の本題は彼の最初の妻であるヴィヴィアン・エリオットについてです。
偉大な作家とされるエリオットの創作の源泉とされながら、搾取されるだけ搾取され、必要がなくなれば捨てられてしまうヴィヴィアン。少しでも規範から外れれば女性はヒステリー、男性は天才と言われた時代に彼女もまた『The Yellow Wallpaper』の名もなき女性と同様、女性の精神疾患に対する無理解や偏見、抑圧的な治療に苦しめられ、最後は強制入院させられた精神病棟で亡くなってしまいます。
長年エリオットのミューズとして、そして狂気の妻として一面的にしか語られてこなかった彼女ですが、近年では、彼女自身の声や創造性に焦点を当てたフェミニズム的観点から再評価が進んでいます。日本でも2021年にヴィヴィアンの生涯に迫る『化粧する影』(松柏社)が2020年に翻訳出版されました。
しかし、その帯には「詩人エリオットの知られざる世界」「一石を投じる問題作」という言葉が並び、結局は夫エリオットの功績や背景としてしか語られていないのです。原書のテンション感が分からないですし、貴重な資料であることは間違いないと思うのですが、それにしても、あんまりでは。
これはフェミニズムに限らず、どんな分野でもそうだと思いますが、特定のジャンルを謳う本を生む過程でそこに携わる人々、つまり翻訳者や編集者、出版社の目線合わせができていないとこのようなズレやノイズが生じてしまうのかなと、勝手に想像しています。このケース以外にも翻訳者による解説の不正確さや残念な認識が露呈したあとがきなどが話題になるたび、やはりフェミニストによって書かれた本はフェミニストに翻訳してほしいなと思ってしまいます。もちろん、常に完璧な環境を用意するのは難しいと理解していますが、それでも強い意思を感じる本というのはあり、その信頼のもと手に取る本を選びたいし、周辺化されてきた女性たちの声を翻訳という行為を通して語り直したいなぁなんて思う今日この頃でした。
というか、『化粧した影』ってなんか嫌味っぽくないですか。影の分際で化粧してやがるって馬鹿にしてませんか。考えすぎですか。そうですか。
気がつけば、ストライキを起こす「彼女」も、神経を衰弱させる「彼女」も、怒りを力に変えて書く「彼女」も、無かったことにされそうな「彼女」も、皆んな、わたしでした。
それでは今回はこんなところで。お読みいただきありがとうございました。良い週末を。
すでに登録済みの方は こちら